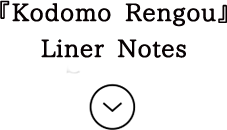
ある意味ではPeople In The Boxというロック・バンドの魅力の言語化しづらさは、国内でも指折りかもしれない。かつて彼らが日本のポストロックの中心地であるレーベル〈残響record〉に所属していたことから、このバンドをポストロック~マスロックのフォルダに入れようとするリスナーやメディアはいまだに多い。たしかにそういう捉え方も間違いとは言えないが、そういったカテゴリーに彼らを入れてしまうと、このバンドの異様さを決定的に捉え損なうだろう。だからぼくはここで、People In The Boxにとって約3年半ぶりの新作となる『Kodomo Rengou』を通して、彼らがどういうロック・バンドなのかを楽曲の構造と歌詞の二つのレイヤーに分けて紐解いてゆきたいと思う。もちろん二つのレイヤーは相互に貫入しあうものだけれど、視点をクリアにするためにあえてそのようにする。
⇨ 続きを読む
まずは楽曲の構造に注目しよう。本作に収録されている楽曲は、基本的にはシンプルなヴァース-コーラス形式で構成されているにもかかわらず、各セクションが様々な方法で繊細かつダイナミックな変奏がなされている。メロディは同じだがリズム・セクションの構造が全く違ったものになっているとか、その逆であることもしばしばだし、様々なアレンジメントによって展開は無数の様相を見せる。たとえ展開が複雑であっても、あくまでに自然に聴こえるのは、明確な形式を備えたうえで、音楽における時間の不可逆性に基づいた作りになっているからだろう。こういった曲の展開は、例えばブライアン・ウィルソンやアンディ・パートリッジが得意としていたし、波多野が敬愛するジェフ・バックリィもそういった不可逆的なサウンド・デザインを度々採用してきたことを考えると、この構造はポップ・ミュージックの王道を行っているともいえる。だからポストロック・バンドというマインドで彼らの楽曲を聴くと、その本質を聴取できないかもしれない。
「町A」の構造について、詳しく言及することからはじめよう。この曲のおおまかな構成は、V(ヴァ―ス)-CH(コーラス)-V-CH-CH-codaだが、先述したように練り込まれた構成になっている。例えば、二度目のヴァース〈羽根を焦がす太陽~〉は最初のヴァ―ス〈ここは天国ではない〉の変奏で、コーラス〈巨大なショッピングモール~〉を経ることでどこか暗く影を落とす雰囲気になっている。これは楽曲の展開と歌詞が秘める物語性が密接に繋がっていることを示す。その一度目のコーラスの最後の部分にはコーダ〈差しあたっては奇跡には用はない~〉が少しだけカットインする。キーボードの即興的なソロがユニークなブレイク、そして再びコーラス〈田畑に~〉を経て全貌を現したコーダ〈差しあたっては奇跡には用はない~〉は、カットインの時と違って長い分どこか現実味を帯び、そのときに歌詞においては主体が明らかに醒めていることがわかる。最後はイントロがリプライズされて終了する。
このように楽曲を巧みに展開させてゆく手法は本作の随所で聴ける。ドラスティックな展開の快楽ということなら、「町A」と匹敵するダイナミズムを持つ「デヴィルズ&モンキーズ」や、メロディの展開はほぼ同様ながらアレンジメントがどんどん変容していく「眼球都市」、ベースとドラムのリズム・コンビネーションの展開が痛快な「夜戦」などでたっぷりと堪能できるだろう。あくまでバンド・サウンドでこれだけの展開をつけられるところに、People In The Boxがロック・バンドとしていかに突出しているかがわかる。ここで述べておきたいのは、彼らにおける複雑性は例えばプログレッシヴ・ロックやポストロックが陥った「目的としての複雑さ」に捉われているものではなく、あくまで楽曲が描くべき世界観のために、生理的/直観的な判断(これは後述する音色の話と合わせて考えればわかる)から産み出された必然的な複雑性だろうということ。だから彼らの楽曲は冗長な部分はなく、形式が明確なこともありポップに響くのだ。ここにあるのは、全ての楽曲に込められた物語は異なるのだから、それらを支える音楽の形式も同じはずがないという確固たる思想ではないだろうか。
彼らが突出しているのは展開のヴァリエーションだけではない。バンド・サウンドを構築してゆく際の、リズム構造にも驚くべき洗練がある。それがわかりやすいのが「世界陸上」だ。ミニマル・ミュージックのように個々の楽器の要素が直線的なフレーズを形成しながら構造を形成し突き進んでいくこの楽曲は、このバンドのプレイヤビリティの高さを物語っており、それをポップス的な展開にきちんと落とし込む作曲的な手腕は驚くべきところがある。ヴォーカル・メロディと鍵盤のリフレインが楽曲をポップなものに引き立てつつ、鋼のように強靭に刻まれるベースラインと繊細なドラムワークのコンビネーションがそれを支えており、ポリリズムの快楽が聴き手に押し寄せてくる。
むろん、楽曲の構造以外にも彼らの魅力はある。例えば、波多野の何気ないハミングに導かれながら始まるオープニング・ナンバー「報いの一日」。この楽曲で注目すべきは、冒頭の奇妙な音色のギターフレーズだ。最初は音色が独立して聴こえるため違和感として存在していたフレーズが、少しずつ曲の機能に回収されてゆき、結果その奇妙さは必然的なものだと感服させられる。他にも一聴してギターには聴こえない「泥棒」や「夜戦」におけるブラスのような音色はじつに面白いし、ギター以外でも最終曲「ぼくは正気」の不整脈のようなベースには驚かされた。こういったサウンドが成り立つのは奇をてらうのではなく、当然そこにあるモノとして、楽曲が持つ物語の中で違和感を創出しているからこそ可能な芸当だろう。こういった言語化できない正解を探り当てるところが、People In The Boxの面白いところだ。
リフレインの中毒性も彼らの持ち味といえる。先述した「報いの一日」の奇妙な音色のギターリフもそうだし、先述した「世界陸上」も巧みなリフレインでリスナーの耳を引き付ける。中でも取り分け注目すべきは「泥棒」のギターリフだろう。この楽曲は終始ギターリフが骨格として機能しており、いわゆる派手なロック・ギターという感じではなくどちらかといえば地味なものなのだが、聴いているうちにじわじわと癖になってくる。
多彩な展開、緻密なリズム構造、不可思議な音色、リフレイン。こういった要素が絡み合うことで、People In The Boxのポピュラリティが生成されてゆくのだ。
歌詞とメロディのレヴェルにフォーカスを移しても、面白い発見がたくさんある。波多野が書く歌詞はメッセージ・ソングやラブ・ソングといった明確な形式を採用していない。何について歌っているのかが、さっと一聴しただけではストレートに伝わってくることが無い場合も多々ある。波多野の繰り出すメロディは極めてバラエティに富んでいてユニークなものだが、そこに当てはまる言葉を飲み下すのには時間がかかる。それにも関わらず、このバンドの歌詞とメロディはポップに響く。この理由については本作を通して丁寧に書いていこうと思う。
最初のポイントは記号&メロディの操作による中毒性だ。例えば「無限会社」では、〈キャンディー〉~〈サルヴァドール・ダリ〉や〈びっくり〉~〈ぴったり〉といった押韻の手法がとられている。このように押韻を単独で取り上げても別段面白いことはないが、これをメロディと絡まった形で仕上げることで、意味を介在することなく中毒性を伴ってリリックが体に入ってくる。この曲よりは柔らかい形で使用されているが「町A」の〈アイムハッピー、ゴー、ラッキー〉や、「動物になりたい」の〈ビスケット〉~〈アルファベット〉、「眼球都市」の〈エレクトリカル〉~〈フラクタル〉といった部分でも同様だ。
こういった中毒性は押韻以外にも固有名詞の使用にも現れる。
例えば「町A」の〈巨大なショッピングモール、レストラン、図書館~〉といった様々な建物の名前が羅列された部分や、「デヴィルズ&モンキーズ」の〈ジェームス・ディーンにマリリン・モンロー〉といったハリウッド俳優・女優の名前が波多野の人懐こい声でメロディに絡めて歌われると、どうしても頭にこびりついてしまう。また、今挙げた言葉たちは明確な物語を伝達しないまでも、それぞれ固有のイメージを保持しており、そのイメージが楽曲のアンビエンスを形成しているところにも注目したい。
他にも、ヴォーカルには反映されていないが、「眼球都市」の歌詞カードにはフレーズの間にスラッシュが入っていたり、聴覚に還元されない、ポストモダン文学にて散見されるような視覚的な面白さも波多野は取り入れている。
意味が宙づりになったフレーズたちが、音楽の中で固有のリズムを持って踊りだし、半透明な物語を形成する。共感でもなければ、拒絶でもないこの音楽的なリリシズムはPeople In The Boxの真骨頂といえるだろう。このバンドにとっての歌詞は、意味性とは別に、それそのものを快楽として享受できるのだ。
とはいえ、こういったフレーズ選択のユニークさだけが彼らの魅力ではなく、本作には「あの人のいうことには」や「かみさま」のように、リスナーの心にストレートに響くフレーズを持つ楽曲もある。
〈これから起こることぜんぶ
息が止まるくらい美しい
ひとはそれを
狂気というけど
ねぇ、きみはほんとうに知ってた?
ねぇ、きみはほんとうに知ってた?
この完璧ではない世界で
人生って一度しかないこと〉
「あのひとのいうことには」
〈かみさまはいつだって優しい嘘をつく
きみは特に優れているとか
きみは報われるだとか
手を伸ばしても空を切る
滑稽な鳥の墜落をみてた〉
「かみさま」
特に「かみさま」は、本作の中で最もメロディと歌詞の結びつきがストレートなギターロックで、おそらくPeople In The Boxのキャリアの中でも屈指の名曲といえるだろう。静と動のメリハリある構成を軸に、カタルシス溢れるギター・ノイズや定位が繊細にコントロールされたドラム、空間のバランスを巧みな感性で整えるベースが恐るべき完成度で成立しており、そこから導き出されたあまりにも優しく切ない〈おはよう おはよう 今日はいい天気だよ〉というフレーズは、リスナーの胸を打つ。
People In The Boxには居場所がない。国内外を問わず、ロック・シーンからは明らかに浮いているし、かといって同時代の音楽を参照しながら作曲をすることも(おそらく)ほぼないため、新しい音楽を熱心に追う層に受け入れられるタイプでもない。〈残響record〉をチェックしているようなポストロック好きに引っかかるタイプの音楽性かといえば、それもまた違うだろう。しかしもう一方で、彼らは日本クラウンに所属し、メジャーを主戦場にしているロック・バンドであるという事実がある。大衆の支持をきっちりと受け、結果を出してきているのだ。つまり、ベタな共感のメカニズムとは距離を取りながらも、独自のポピュラリティを獲得しているということになる。ここで散々書き連ねてきたように彼らのサウンドには途方もない魅力があるのだ。『Kodomo Rengou』からはスティーヴ・ライヒやロバート・ワイアットの音楽が聴こえてくる気がするし、この作品はグリズリー・ベアやザ・ナショナルの新作と並べて聴くことができるという確信がぼくにはある。どこまでも明晰な音楽である一方で、どこまでも解釈の網の目を潜り抜け続けるPeople In The Boxの音楽は、これからも人々の耳に快楽と謎を提供し続けることだろう。
八木皓平 (音楽批評家)
© People In The Box All Rights Reserved.